【座談会】日福で得られたのは教員や仲間との一生もののつながり
精神保健福祉士を目指すなかで、知識や資格と同じくらい大切なことが「自分を知る力」や「人との向き合い方」です。日本福祉教育専門学校(以下、日福)では、現場経験が豊富な教員が学生一人ひとりに寄り添い、支援職としての土台を育む学びを展開しています。今回は、精神保健福祉士養成学科の卒業生4名が、教員と共に「教員と学生のつながり」をテーマに語り合いました。


現場経験を活かした実践的な授業に定評があり、依存症支援や家族支援など幅広い分野での知見を持つ。卒業後も学生との交流を続け、OB・OGが気軽に集える勉強会なども主催している。

前職は警備会社勤務。30代の頃から福祉に関心を持ち、50代でキャリアチェンジを決断。現在は地域の就労支援・生活支援員として活躍している。

前職はIT企業で総務を経験。障害者雇用業務がきっかけで福祉の道へ。現在は精神科クリニックに勤務している。

前職は地域の相談施設に勤務。支援の中で精神保健福祉士の役割に気づき、資格取得を決意。現在は障害者雇用の現場で就労サポートを行っている。

子どもの居場所づくりや遊び場づくりの実務経験を経て、より実践的な支援スキルを求めて日福で学び直しを決意。現在は精神科病院に勤務。
※インタビュー当時の情報です
「もどかしさ」が学び直しのきっかけに
ー皆さんが福祉の道に進もうと思ったきっかけを教えてください。

前職は警備会社に勤めていましたが、50代になり改めて自分のキャリアを考えた結果、この道に進もうと決意しました。実は30代の頃に福祉の資格取得を考えたことがありましたが、そのときは会社を辞める決断ができませんでした。でも50代になり、弟が入院したことなどをきっかけに、医療と生活の間を支えるような役割の必要性を強く感じるようになりました。最初は社会福祉士を考えていましたが、病院などと連携して支援していく精神保健福祉士という資格のほうが、自分のやりたいことに近いと思えたため、今の学科を選びました。

私も白根さんと同じく異業種からのキャリアチェンジです。もともとIT企業の総務部で働いていました。ちょうど障害者雇用の制度が整い始めた時期で、採用業務にも関わっていたのですが、障がいのある方を受け入れる体制が整っていないことにもどかしさを感じていました。書類上は「採用」しても、それだけでは支援にはならない。現場の中でどうすれば働きやすくなるのか、自分はまだ何もできていないと痛感したんです。その後、医療事務の仕事も経験しましたが、次第に「もっと支援の現場に関わりたい」という気持ちが強くなり、この資格を取ろうと決めました。

私は元々、精神疾患や依存症のある方の就労支援に携わっていました。ただ、就労支援の現場で「専門知識がない中で、本質的な関わりができていないのでは」と感じ、学び直しを決意しました。最初は友人の勧めで看護師を目指していた時期もありました。ただ、母が社会福祉士で幼い頃から福祉に興味があったことや、自分の適性なども考える中で、精神保健福祉士がぴったりだと思い至りました。実は、日福のこの学科を見つけたのは、願書受付締め切り直前の2月末です。そこから面接を受け、ほとんど勢いで入学しましたね。

私は、子ども向けの居場所づくりや、地域の遊び場づくりに長く関わってきました。年齢も立場もさまざまな人たちと関わる中で、ちょっとした雑談の中で深刻な事情が垣間見えても、具体的な手立てを示すことができなかったんです。そこから、「もっと実践的な引き出しがほしい」という想いが強くなり、進学を決意しました。日福を選んだ決め手は、信頼していた職場の先輩が日福出身だったことです。通っている人の顔が見えたのが大きかったですね。

授業だけでなく「教員のふるまい」で
支援のリアルを学んだ
ー在学中に印象に残っている授業はありますか?

私は正直、入学前は「学生に戻る」ことに少し抵抗がありました。でも岡﨑先生の授業を受けて、「これはただの座学じゃない」と思ったのを覚えています。制度や法律の話だけじゃなく、実際にあった現場のケースを交えて話してくださるので、一つひとつの内容が自分事として入ってきました。

わかります。教科書の内容を覚えるというより、「本当にそういう人がいる」「実際にこんな支援をしてきた」という話を聞くと、印象に残りますよね。私は、精神科医の非常勤講師の方の講義が特に印象的でした。診療の現場で感じている違和感や葛藤を率直に話してくださって、専門職のリアルに触れられた気がしました。

私が印象に残っているのは、教室を飛び出して実際の現場を体験する授業です。特に岡﨑先生に誘っていただいて訪れた、自助グループや依存症の回復施設の見学は忘れられません。当事者の方の言葉を直接聞き、これまで知らなかった空気感やリアルな声に触れた経験から、支援はまずその場所に行き、自分で感じることから始まるのだと実感しました。

私たち教員は、それぞれが現場での経験を持ったうえで教壇に立っています。その経験を最大限に活かし、ただ制度を教えるのではなく「その制度をどう使うか」「そのとき自分はどう感じたか」を一緒に考えられる授業を意識しています。教室の中に、少しでも現場の空気が流れるような時間を作れたらと思っています。
ー授業以外での先生との関わりで印象的なエピソードはありますか?

国試が差し迫った期末試験の初日、問題に取り掛かろうとすると手が震えて、涙が止まらなくなった時がありました。休憩スペースで5時間ほど動けずにいたとき、先生方が気づいて声をかけてくださり、静かに話を聞いてくれました。「頑張ってきたからこそ気持ちが揺れているんだよ」と言ってくださって、その言葉で肩の力が抜けました。寄り添ってはくれるけれど、入り込みすぎない。その絶妙な距離感から、支援の姿勢そのものを学んだと思います。

絶妙な距離感という話はすごくよく分かります。私も実習中に、精神科の現場で身体拘束の場面に立ち会い、強い衝撃を受けた時がありました。気持ちの整理がつかず、泣いてしまうほど追い詰められました。その際に岡﨑先生に相談したときは、まず「感じたことをそのまま話していい」と言ってくださったのが印象的です。じっくりと時間をかけて、話を無理やり聞き出そうとはせず、一緒に考えてくれる。寄り添ってもらったことで、気持ちが落ち着き、自分の考えを持ち直すことができました。

この二人のように学生それぞれが、違った不安や葛藤を抱えていると思っています。ただ、全員とじっくり話すのは現実的には難しいこともあるので、日々の様子やレポートの中に表れる変化にできるだけ気を配るようにしています。
ただ、学生はクライエントではないため直接的な支援を行うわけではありません。学生が将来、ソーシャルワーカーとして現場に立てるようにサポートするのが教員としての役割だと思っています。どこまで踏み込むか、どこまで見守るか。支援のバランスを体感として学んでほしいという思いを持って、日々接しています。

卒業後こそ感じる「つながり」の強み
ー日福での学びの中で、卒業後に特に役立っていると感じることはありますか?

在学中に何度も言われた「自己覚知」という言葉が、今もずっと頭に残っています。自己覚知とは、自分自身の感情や思考などを認識することなのですが、最初は正直、自分に向き合うことが苦手でした。でも実習や授業を通じて、少しずつ「自分の感じ方の癖」や「反応のパターン」が見えてくるようになりました。支援の現場では、自分の感情や価値観が知らず知らずのうちに表に出てしまうことがあります。それに気づけるかどうかで、相手への関わり方が大きく変わってくると実感しています。

それは本当にそうですね。私は岡﨑先生の出すレポート課題が「自己覚知」するうえでとても力になったと思います。最初は書くことが苦手だったのですが、課題を通して「なぜそう思ったのか」を掘り下げるうちに、考えが整理され、自分の中にある価値観や視点に気づけたことが何度もありました。今の仕事でも、つまずいたときに「言葉にすること」で立ち戻れるようになったと思います。

私は、現場で子どもと関わる中で感情が揺れることが多くて、最初はその感覚に戸惑ってばかりでした。でも、先生方が「書いて残すことが、次の支援につながる」と言ってくださったことで、無理に正解を出そうとしなくなりました。あの頃、自分の感情や反応をそのままノートに書き留めていたことが、いま現場で一番役立っています。

「自己覚知」に終わりはありません。支援の現場に出てからこそ、新たな自分に出会い続けるものです。そのたびに「なぜ自分はこう感じたのか」と言語化する力があると、相手の話にもより丁寧に耳を傾けられるようになります。また、精神保健福祉士は「書く仕事」が多いんです。その点でも、レポートや振り返りの習慣を身につけることはとても大切です。学生からは大変という話をよく聞きますが、必ず将来に活きると思います。

ー卒業後は先生や同級生とどのような交流がありますか?

日福の一番の魅力は、卒業生同士や先生との交流が活発なところだと思います。学科としては卒業生同士で事例検討を行う「臨床ソーシャルワーク研究会」「精神保健福祉研究科」が開催されており、それとは別に岡﨑先生主催の、近況報告を兼ねたOBOG会もあります。
私はこれらの会に定期的に参加しています。特に研究会では、現場での対応に悩んだときに他の人の意見を聞けるのが心強いです。また、他の参加者の話から知識や視点をアップデートできる点も、大きな魅力だと感じています。もしかしたら、在学中よりも今の方が先生にいろいろ相談しているかもしれません。

私はOBOG会に何度か参加しています。研究会と違って雑談会のようなラフな雰囲気で、仕事が忙しいときでも参加のハードルが高くないのがありがたいです。近況を話したり、他の方の話を聞いたりするだけでも気持ちが整理されて、翌日からまた頑張ろうと思えます。

雑談の中で出た話が、後になって自分の現場で生きてくることもあります。同じ学校で学んだ人同士の安心感があるから、どんな話題でも構えずに話せます。「帰ってきてもいい場所」があると思えることは、本当にありがたいですね。

実際に仕事をしていると、利用者さんへの対応だけでなく、職場内の人間関係など、なかなか職場では話しにくいことも出てきます。そういった話を、日福のOBOG会では自然にできる。専門的な相談も含め、福祉の仕事をしている仲間として話し合える空気があるのが、この場の良さだと感じています。

培った関係性とネットワークが
卒業後の支えになる
ー入学を検討している方にメッセージをお願いします。

学生時代、私はあまり自分のことを話すのが得意ではありませんでした。でも、日福ではどんな自分でも受け止めてくれる仲間に出会えました。弱音を吐いても、LINEで気持ちを打ち明けても、それを「ダメなこと」とせずに話を聞いてくれる人たちがいて、日々救われています。これから先の人生を一緒に歩んでくれる仲間に出会えたことが、今も支えになっています。

この学校の魅力は、年齢も職業も違う人たちが集まっているところです。それぞれの経験や立場が違うからこそ、自分の視野も広がっていくのを感じました。日福で出会った人たちとのネットワークが、今の仕事でも助けになっています。困ったときに相談できる相手がいるというのは、本当に心強いことです。
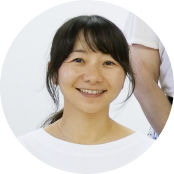
私はもともと勉強があまり得意ではなかったので、最初は不安もありました。でも、通学して学ぶ中で、いろいろなバックグラウンドの人たちと出会って、「自分とは違う考え方」と向き合う時間がすごく豊かでした。卒業してからも、例えば「ボランティアに行こう」などと誰かが提案すると「一緒にやってみよう」と自然に応えてくれる仲間がいる。そんな環境が、何よりも魅力だと思います。

支え合える仲間と先生方との距離感、それが日福の一番の魅力だと感じています。自分の職場では、他校出身の方は卒業後に学校との関係が切れてしまうという話をよく聞きます。でも、日福は卒業してからもずっとつながれる場所です。事業所や施設には日福出身の方が多く、「日福出身」と言うだけで信頼されるような空気があります。また、先生方も卒業しても親身に話を聞いてくださる。このネットワークと関係性の強さは、働いていくうえでも心強く感じます。

皆さんがおっしゃる通り、さまざまな経歴や年代の方が集まって、それぞれに違いがあるからこそ、お互いを支え合う関係が育まれています。経験のある方が若い人から学ぶこともあれば、逆もまた然りです。そうした「違いを活かし合う」関係性が築けているのは、私たち教職員にとっても誇らしいことです。福祉に関心を持ったその気持ちを、まずは信じてみてください。きっと、ここでなら一歩を踏み出せるはずです。


踏み出そう
日本福祉教育専門学校では、福祉・医療の専門家を目指す皆様を全力でサポートします。まずは資料請求やオープンキャンパスで、学校の雰囲気を感じてみてください。











