【2025年最新版】社会福祉士とは?役割から仕事内容、他資格との違いなど
少子高齢化や社会的孤立の深刻化により、福祉の専門職である「社会福祉士」への注目が高まっています。生活に困難を抱える方々の相談援助を担う国家資格として、幅広い分野で活躍する社会福祉士ですが、その役割や具体的な仕事内容、他の福祉系資格との違いについて正確に理解している方は多くありません。
本記事では、厚生労働省などの公的情報をもとに、社会福祉士の定義や業務内容、年収、将来性、取得方法などを解説します。
目次
社会福祉士とは?役割と重要性

少子高齢化や地域の分断が進む現代社会において、人々の生活課題はますます多様化・複雑化しています。そうした課題に対応する専門職として、社会福祉士の存在が重要視されています。社会福祉士とは国家資格を有する相談援助の専門家であり、医療・高齢者・障害・子ども・生活困窮といった幅広い分野で支援を行います。
ここでは、社会福祉士の法的な定義や専門的役割を見ていきましょう。
社会福祉士の主な役割と機能
社会福祉士の職務は多岐にわたりますが、その中心は「相談援助」です。
現場では、以下のような具体的役割が求められます。
- 生活課題を抱える人の相談に応じ、解決に向けた助言や計画立案を行う
- 福祉制度や介護保険、生活保護、障害者支援など公的制度の活用を支援する
- 医療・介護・教育など他分野の専門職と連携して、地域包括ケアを推進する
- 家庭や地域に働きかけ、環境改善や差別解消に向けた社会資源の調整を行う
- 被援助者の権利擁護(アドボカシー)を実践する
単なる対人支援にとどまらず、制度と人、現場と政策をつなぐ「社会の橋渡し役」としての機能も担っています。
社会福祉士が果たす社会的意義
社会福祉士は、個人や家庭への支援を超えて、社会全体の福祉向上にも寄与しています。
その重要性は、次の点に集約されます。
| 社会的意義 | 説明 |
|---|---|
| 社会的包摂の促進 | 排除・孤立された人々を制度に結びつけ、誰もが暮らしやすい社会を実現する |
| 多職種連携の要 | 医療・教育・介護の各現場で調整役となり、支援の質を高める |
| 福祉の専門性の担保 | 国家資格として制度に裏付けられた支援を提供し、職務の透明性と信頼性を保つ |
| 地域共生社会の推進 | 地域で完結する支援体制の中核を担い、共助の社会づくりに貢献する |
社会福祉士の存在は、単に「福祉の担い手」ではなく、社会構造のセーフティネットを支える基盤となっているのです。
通学なら1年で社会福祉士に!日本福祉教育専門学校

国家試験 合格者数全国 No.1
ライフスタイルにあわせたコースを用意。
1年コースで資格取得を目指す昼間部・夜間部、選べるスクーリング会場と日程が特長の通信教育部を設置しています。
社会福祉士養成学科(昼間部)を詳しく見る ▶
社会福祉士養成科(夜間部)を詳しく見る ▶
社会福祉士養成の通信を詳しく見る ▶
社会福祉士の仕事内容と勤務先

社会福祉士の仕事は、相談援助という枠を超えて、制度と現場をつなぐ調整や支援のコーディネートにまで及びます。活躍の場は多様であり、福祉施設はもちろん、病院、行政機関、学校など社会のあらゆる領域に広がっています。
ここでは、社会福祉士がどのような現場で、どのような支援を行っているのかを整理しましょう。
社会福祉士の主な仕事内容
社会福祉士の中心業務は「相談援助業務(ソーシャルワーク)」です。対象者の課題や生活状況に応じて、適切な制度・資源と結びつけ、自立に向けた支援を行います。
以下は、主な業務内容です。
●生活課題のアセスメント(課題把握)
家庭環境・経済状況・心身の状態などを多角的に調査し、支援計画を立案します。
●相談援助と制度活用の支援
介護保険・障害福祉サービス・生活保護などの利用申請を支援し、制度の活用を促進します。
●多職種連携・調整業務
医師、看護師、ケアマネジャー、教員などと連携し、包括的な支援体制を構築します。
●権利擁護・アドボカシー活動
認知症高齢者、障がい者、子どもなどの意思を代弁し、社会的排除を防ぎます。
●地域ネットワークの構築
地域包括ケアの実現に向けて、NPO・行政・医療との協働による支援体制を築きます。
このような業務は、対象者の属性や職場によって柔軟に変化し、専門性と倫理性が常に求められるでしょう。
社会福祉士が活躍する主な勤務先
社会福祉士の資格は、多様な分野で活かされます。以下の表に、勤務先ごとの主な役割を整理しました。
| 勤務先の種類 | 主な役割・業務内容 |
|---|---|
| 地域包括支援センター | 高齢者の総合相談、介護予防プランの作成、支援ネットワークの調整 |
| 医療機関(病院) | 医療ソーシャルワーカーとして、退院支援・医療費相談・在宅サービス連携 |
| 福祉施設(高齢・障害・児童) | 利用者支援、家族対応、施設運営の調整・相談対応 |
| 行政機関(福祉事務所など) | ケースワーカー、生活保護受給者の支援、制度運営 |
| 児童相談所 | 虐待対応、子どもと家庭への支援、施設や学校との調整 |
| 学校・教育機関 | スクールソーシャルワーカーとしての子ども支援、保護者との連携 |
| NGO・NPO | 地域活動、ホームレス支援、被災者支援、若者就労支援など |
出典:
社会福祉士は、医療・福祉だけでなく教育、司法、災害支援などでもその専門性を求められており、地域社会のあらゆる課題に対して「つなぐ役割」を担う職業といえます。
社会福祉士のキャリアパスと将来性
社会福祉士は、資格取得後もさまざまなフィールドで経験を積みながら、専門性を高めていくことが求められます。
現場経験を活かした昇進、行政職への転職、さらには独立開業といったキャリアパスが開かれており、福祉業界の中でも柔軟性のある職種といえるでしょう。また、社会全体の変化により、社会福祉士の役割とニーズは今後ますます拡大すると考えられています。
社会福祉士の主なキャリアパス
社会福祉士として働いたあとに目指せるポジションや職務の例を以下に整理しました。
●相談援助職からの昇格
福祉施設などでは、生活相談員や支援員から主任・施設長へ昇進するケースが多く見られます。
●行政職へのキャリアチェンジ
福祉事務所や自治体の福祉関連部署に採用され、ケースワーカー、行政相談員などの職種に移行する例もあります。
●専門領域のスペシャリスト化
高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、医療ソーシャルワークなど特定分野に特化し、チームリーダーやスーパーバイザーになる人も多くいます。
●独立・開業
一定の条件を満たせば、フリーランスとして「独立型社会福祉士」として活動することも可能です。社会福祉士事務所の設立やコンサルティング業務を行うケースもあります。
●上位資格の取得
「認定社会福祉士」や「精神保健福祉士(共通科目一部免除)」など、さらに専門性を高める上位資格取得も有力なキャリア展開の一つです。
キャリアの幅が広く、相談援助職の専門性を軸に、多様な道へと進める柔軟性のある国家資格であることがわかります。
社会福祉士の将来性と社会的ニーズ
社会福祉士の将来的な需要は、国内の人口動態や社会構造の変化を背景に、今後さらに高まると考えられています。
| 将来性を支える要因 | 内容 |
|---|---|
| 高齢化の進行 | 2025年には65歳以上の人口が全体の約30%に達する見通しで、高齢者支援のニーズが増加。 |
| 地域共生社会の推進 | 厚生労働省が「我が事・丸ごと」支援体制を掲げ、地域で完結する包括的支援が政策目標に。 |
| 医療・福祉連携の強化 | 医療ソーシャルワーカーや退院支援など、社会福祉士の連携・調整力が必須に。 |
| 社会的孤立と困窮への対応 | 8050問題、ヤングケアラー、生活困窮世帯の支援など、複雑化する課題への専門職が求められる。 |
| 福祉の専門性への期待 | 資格保有による信頼性、倫理性、継続的研修など、専門職としての地位が制度上も強化されつつある。 |
出典:
このように、社会福祉士は「困難を抱える人に寄り添う支援者」であると同時に、持続可能な地域社会を支える専門職としても今後の福祉政策の中心を担っていくと期待されています。
社会福祉士として働く方の年齢層や性別
社会福祉士の資格保有者は年々増加しており、その年齢構成や性別には一定の傾向があります。福祉分野での働き方や職場の特徴を知るうえでも、年代別の分布や男女比を理解することは非常に重要です。
ここでは、社会福祉士として働く方々の属性傾向を見ていきましょう。
年齢層の傾向:30代~50代が全体の7割を占める
就業中の社会福祉士の年齢構成を見ると、30代・40代が最も多く、次いで50代となっており、キャリア中堅層が中心となって現場を支えていることがわかります。
| 年齢階層 | 割合(令和元年調査) |
|---|---|
| 20~29歳 | 約12.8% |
| 30~39歳 | 約27.3% |
| 40~49歳 | 約30.3% |
| 50~59歳 | 約22.3% |
| 60歳以上 | 約7.2% |
出典:厚生労働省「社会福祉士等の就業実態等調査結果報告(令和元年)」
このように、社会福祉士の中心世代は30〜50代であり、一定の経験と専門性を持つ中堅層が多いことが特徴です。
また、20代の若手や60歳以上のベテランも一定数存在し、幅広い世代で専門性が活かされている職業といえるでしょう。
性別の傾向:女性が約7割を占める
同じ調査によると、社会福祉士の性別構成は女性が約71.3%、男性が28.7%となっており、福祉分野の他職種と同様に女性が多数を占めている現状が明らかになっています。
この背景には、福祉の現場が高い共感力や協調性を求める傾向があること、またライフスタイルに合わせた働き方がしやすい職場が多いことなどが影響していると考えられます。
とはいえ、近年では男性の社会福祉士も徐々に増加傾向にあり、児童福祉や生活困窮者支援、行政分野などでは男性のニーズも高まっている分野があるでしょう。
関連記事:女性が活躍できる社会福祉士の仕事
社会福祉士の年収
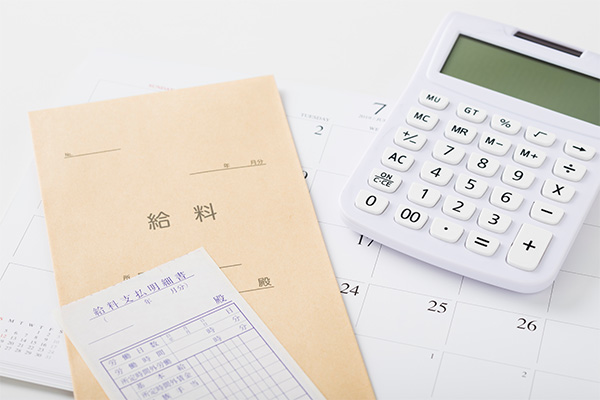
社会福祉士の年収は勤務先や職種、地域、経験年数などによって差がありますが、厚生労働省の「令和6年 賃金構造基本統計調査」によると、社会福祉士を含む「その他の保健医療従事者」の平均所定内給与額は月額288.1千円(=288,100円)となっています。この統計の誤差率(相対標準誤差)は2.7%で、信頼性の高い数値といえます。
この月給に加えて、年間賞与などの特別給与を加味すると、平均年収はおおよそ420万~430万円程度と推計されます。年収は月額給与×12カ月分に、夏季・冬季のボーナス(賞与)分を加算する形で算出されますが、ボーナス支給の有無や額は雇用形態・勤務先により異なるため、実際には個人差があるでしょう。
実務上では、福祉施設や病院に勤務する常勤の社会福祉士であれば、おおよそ年収400万円前後が目安とされます。
一方、非常勤・パート勤務の場合は年収300万円未満となることもあり、雇用形態によって収入に大きな差が生じるのが実態です。
また、地方自治体の行政職や大規模医療機関に勤務する社会福祉士では、年収500万円以上となるケースもあります。特に管理職や施設長などに昇格すれば、さらに高収入が期待されるでしょう。
近年は福祉人材の確保や待遇改善に向けて、厚生労働省が処遇改善加算制度の導入や資格手当の推奨など、政策的支援を進めています。そのため、社会福祉士の職域における給与水準は今後も緩やかに上昇する可能性があります。福祉分野においては比較的安定した国家資格であり、キャリアと専門性を積み重ねることで収入向上の道も開かれているといえるでしょう。
出典:厚生労働省「令和6年 賃金構造基本統計調査」
社会福祉士になるには?受験資格など資格取得までのステップ
社会福祉士になるためには、国家試験に合格したうえで厚生労働大臣への登録を行い、正式に名簿に登載される必要があります。その前提として、受験資格を満たす必要があり、学歴や実務経験によって複数のルートが用意されています。
ここでは、資格取得までの基本的な流れと、それぞれの受験資格ルートを見ていきましょう。
資格取得の基本ステップ
社会福祉士になるには、国家試験の合格と登録が必要です。
資格取得の流れはシンプルですが、受験資格を得るまでに一定の学歴または実務経験が求められます。
- 受験資格を満たす(主に大学や養成施設の課程修了)
- 国家試験を受験・合格する
- 厚生労働大臣への登録申請を行う
- 名簿に登載され、社会福祉士証が交付される
国家試験は年1回、例年2月に実施されており、3月に合格発表があります。試験は誰でも何度でも受験可能ですが、初回受験には必ず受験資格の取得が必要です。
このように、国家資格としての信頼性を担保するために、社会福祉士になるには段階的なプロセスが整備されています。
受験資格の主なルート
社会福祉士国家試験の受験資格は、学歴と実務経験の組み合わせにより複数のルートがあります。どのルートを選ぶかは、本人の最終学歴や職歴によって決まります。
代表的な受験資格ルートは以下の通りです。
- 福祉系大学の指定科目履修者:大学在学中に必要な科目を修了すれば、そのまま受験可能
- 一般大学卒業+養成施設ルート:福祉と無関係の学部出身者も1年以上の養成課程修了で受験可
- 短期大学卒業者:1〜2年の実務経験を積み、養成施設を修了すれば受験資格取得
- 実務経験者ルート:福祉現場での相談援助業務を4年以上経験し、短期の養成課程(6か月以上)を修了した者
このように、社会福祉士の受験資格は柔軟な仕組みとなっており、新卒者はもちろん、社会人経験者にも開かれた制度設計となっています。
制度変更への注意点
今後、社会福祉士国家試験の受験資格制度や養成課程の見直しが予定されています。
2027年度以降には一部ルートで要件が厳格化される可能性があり、養成機関への進学や受験時期を検討している人は、公式情報を随時確認することを推奨します。
このように、制度変更の動向にも注意を払いながら、自身のキャリア設計に合ったルートを選ぶことが、資格取得への第一歩となるでしょう。
社会福祉士国家試験の合格率や難易度
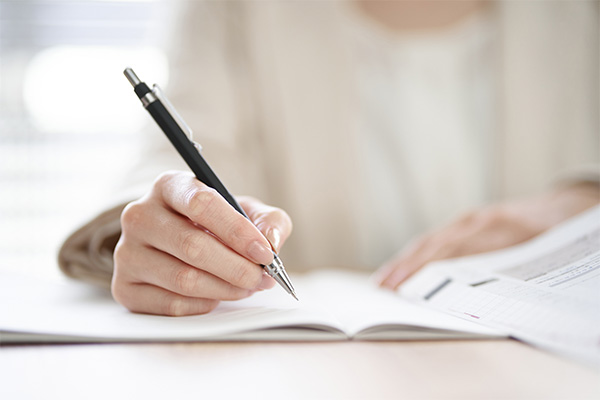
社会福祉士国家試験は、相談援助職としての高い専門性を評価する国家試験であり、年1回(例年2月)に実施されます。
受験には一定の学歴や養成課程の修了が必要で、誰でも自由に受験できる試験ではない分、受験者の質が高く、専門職としての評価も高いものです。
ここでは、令和6年(2025年発表)時点の最新データを用いて、合格率や難易度を探っていきましょう。
第37回国家試験の合格率は56.3%
2025年に実施された第37回社会福祉士国家試験では、受験者数が27,616人、合格者数は15,561人となり、合格率は56.3%でした。
過去10年の中で2番目に高い合格率であり、特に直近数年で合格率は安定的に上昇傾向にあるといえます。
また、同試験において福祉系大学を卒業予定または卒業した新卒者の合格率は75.2%と非常に高いのに対し、既卒者(社会人や独学者など)の合格率は35.8%と大きな差が見られました。
この結果は、学習環境やカリキュラム、指導体制の有無が合否に大きく影響することを示しています。
過去の推移を見ると、平成30年代前半(例:第29回〜第32回試験)はおおむね30%台で推移しており、当時は「難関資格」として認知されていましたが、最近は受験者層の変化や教育体制の強化により、合格率は40〜50%台へと改善されてきました。
| 第34回(2022年2月) | 第35回(2023年3月) | 第36回(2024年2月) | 第37回(2025年2月) | |
|---|---|---|---|---|
| 受験者数(人) | 34,563 | 36,974 | 34,539 | 27,616 |
| 合格者数(人) | 10,742 | 16,338 | 20,050 | 15,561 |
| 合格率(%) | 31.1 | 44.2 | 58.1 | 56.3 |
出典:厚生労働省「社会福祉士国家試験の受験者・合格者・合格率の推移」
関連記事:社会福祉士になるには?受験資格や合格率、国家試験について
合格に必要な勉強時間は約300時間
社会福祉士国家試験の合格に必要な学習時間は、一般的に約300時間程度とされています。
他の福祉系資格と比較して最も長く、たとえば介護福祉士(約250時間)、精神保健福祉士(約250時間)と比べても学習負担が大きい試験であることがわかります。
この学習時間の多さは、主に次の理由によるものです。
- 出題科目数が多い(19科目群)
- 法制度の改正や地域福祉施策の変化が頻繁にある
- 多肢選択や事例問題など、実践的思考力が求められる
- 一定の基礎知識に加えて応用力・統合的理解が求められる
そのため、試験対策には科目の網羅だけでなく、制度改正の情報更新や事例対応の力を養う必要があるでしょう。
難易度は高いが、新卒者には「手の届く国家資格」
社会福祉士国家試験は、範囲が広く専門性も高いため、確かに難易度の高い資格試験といえます。
しかしながら、大学や専門養成機関で体系的に学習を積んだ新卒者にとっては、合格率75%超という高い成功率からもわかるように、十分に到達可能な国家資格です。
一方で、社会人や既卒受験者にとっては以下のような課題もあります。
- まとまった学習時間の確保が困難
- 独学では最新の法改正や出題傾向への対応が難しい
- 学習習慣が途絶えている場合、復習の負荷が大きい
こうした背景から、特に社会人受験者には通信講座や予備校の活用、模試の受験、計画的な学習スケジュールの設計を推奨します。
また、合格ラインに達していても一部科目で極端に点数が低い場合は不合格となることもあるため、全科目を満遍なく学習することが求められるでしょう。
他の福祉系資格との違い
福祉の現場では、さまざまな国家資格や専門職が存在しており、社会福祉士と似た役割を持つ資格も少なくありません。中でも「介護福祉士」「精神保健福祉士」「ケアマネジャー」「ソーシャルワーカー」は混同されやすい存在です。
それぞれの資格の役割や対象者、業務内容、取得方法の違いを把握しておくことで、自分に合った資格選びやキャリア設計がしやすくなります。
資格の種類と業務内容の違い
福祉系資格はそれぞれ、対象とする支援の領域や、求められる専門性、活躍する場に違いがあります。
以下に、主な資格の特徴をまとめました。
| 資格名 | 資格の種別 | 主な業務内容 | 主な勤務領域 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉士 | 国家資格(厚生労働省) | 高齢者・障害者・児童・生活困窮者等の相談援助。制度利用の調整、地域支援。 | 福祉施設、医療機関、行政機関、社会福祉協議会 など |
| 精神保健福祉士 | 国家資格(厚生労働省) | 精神疾患のある人への相談支援。生活支援・就労支援などを行う専門職。 | 精神科病院、保健所、就労支援施設、福祉事務所など |
| 介護福祉士 | 国家資格(厚生労働省) | 身体介護や日常生活の支援を行う現場の専門職。 | 特別養護老人ホーム、訪問介護、グループホームなど |
| ケアマネジャー(介護支援専門員) | 公的資格(都道府県実施) | 介護サービス計画(ケアプラン)の作成と各機関との調整。 | 居宅介護支援事業所、施設系サービス事業所など |
資格は、いずれも福祉や医療と密接に関わる仕事ですが、対象者と提供するサービスの内容に違いがあります。
社会福祉士は支援対象が広範囲であり、相談支援の司令塔のような役割を担います。一方で介護福祉士は、実際の身体介護など、直接支援に特化した資格です。
関連記事:精神保健福祉士とは?
関連記事:介護福祉士とはどんな資格?仕事内容や給料、国家試験など
社会福祉士と精神保健福祉士の違い
社会福祉士と精神保健福祉士は、いずれも相談援助を主たる業務とする国家資格です。
どちらも厚生労働省が所管し、「社会福祉士及び介護福祉士法」および「精神保健福祉士法」に基づいて制度が運用されています。共通点としては、社会的・精神的に困難を抱える人の相談を受け、課題解決に向けた支援を行うという役割がありますが、大きな違いは支援対象と活動領域です。
社会福祉士は、広い領域において、生活に困難を抱える人全般を対象とした支援を行います。具体的には、高齢者、障害者、児童、生活困窮者、引きこもり状態にある若者、被虐待者、刑余者(出所者)など、様々な背景を持つ人々が対象です。支援内容も多岐にわたり、福祉制度や社会資源の紹介、関係機関との連携、地域支援の調整などが含まれます。
一方で、精神保健福祉士は、精神障害者や心の病を抱える人への支援に特化した専門職です。精神科病院、地域生活支援センター、保健所、精神科クリニック、就労支援施設などで活躍し、医療機関との調整や退院後の生活支援、就労への橋渡しなどを担います。とくに精神医療の知識や社会復帰支援の実務が求められるため、医療現場に近い福祉職ともいえます。
両資格は支援対象が異なるものの、支援の重なりが見られる場面も多く、同じ現場で連携することもあります。たとえば、ひとり暮らしの高齢者が精神疾患を抱えている場合、社会福祉士が生活支援全体を調整し、精神保健福祉士が医療面の連携を行うなど、補完関係にあるでしょう。
社会福祉士とケアマネジャーの違い
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護保険制度に基づいて位置づけられる専門職であり、要介護者や要支援者のために介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、各種サービスの調整を行うことが主な役割です。資格試験は都道府県が実施し、介護や福祉、医療に関する国家資格を保有していること、かつ実務経験が5年以上あることが受験要件となっています。
社会福祉士との違いは、主に対象領域と視点の広さにあります。ケアマネジャーは介護保険制度の枠内で活動することが前提で、利用者が要介護認定を受けていることが支援の出発点となります。業務範囲は、ケアプランの立案、サービス事業者や家族との調整、定期的なモニタリング、給付管理など、極めて制度運用に密着したものです。
対して社会福祉士は、介護保険の対象外の人、たとえば生活保護受給者、制度の狭間にいる人、福祉サービスの申請前の段階にある人なども対象に支援を行います。視野が制度全体に広がっており、複数制度の連携や包括的支援、地域とのネットワーク構築が業務の一部となります。
現場では、ケアマネジャーと社会福祉士が連携するケースが多く、たとえば地域包括支援センターでは両者が在籍していることも一般的です。ケアマネジャーは具体的な介護プランを担当し、社会福祉士が制度間の調整や課題の抽出、行政との折衝などを行うことで、相互に支援機能を補っています。
関連記事:社会福祉士とケアマネジャーの違い
社会福祉士と介護福祉士の違い
介護福祉士は、介護サービスの提供を担う国家資格であり、利用者の身体介護(食事・入浴・排泄など)や生活支援を中心とした直接的な支援を行う専門職です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設、訪問介護、グループホームなどで働き、利用者の生活の質を維持・向上させる実践的支援を日々行っています。
社会福祉士は一方で、相談援助と制度調整を担う職種です。利用者の生活上の問題を発見し、必要なサービスの提案、制度利用の支援、地域のネットワーク構築など、生活支援を制度的・社会的に整える役割を持ちます。
両者の違いは、「支援の場面」と「関わり方」でしょう。介護福祉士は利用者の日常生活の現場に常に寄り添い、直接的な身体的援助を行いますが、社会福祉士はその支援を制度面から支える存在として、全体的な生活の再設計や社会とのつながりの回復を支援します。
両者は現場において連携して働くことが多く、介護福祉士が気づいた生活課題や家族関係の問題を社会福祉士につなぎ、制度的な解決を図るといった連携体制が重視されます。また、チームアプローチが求められる医療福祉の現場では、両資格者が対等な立場で専門性を発揮しながら、利用者の支援にあたっているのです。
関連記事:社会福祉士と介護福祉士の違い
どの資格が向いているかは「支援したい相手」と「働き方」で選ぶ
どの福祉資格を目指すべきかは、自身が「誰の支援に関わりたいか」「どのような立場で仕事をしたいか」によって変わります。
社会福祉士は相談援助を軸とした支援の設計者としての役割が強く、現場全体の支援体制を見渡すような仕事がしたい方に向いています。
一方、介護福祉士は直接的なケア、精神保健福祉士は精神医療と地域福祉の橋渡し、ケアマネジャーは制度運用の実務家としての側面が強くなります。
各資格には異なるやりがいや課題があり、それぞれが福祉の現場で欠かせない存在であることに変わりはありません。
目指すキャリアに応じて、資格選択を慎重に行うことが大切です。
社会福祉士を目指せる学科
昼間部、夜間部、通信教育と自分に合った学習スタイルを選ぶことができます。

社会福祉士養成学科
合格者数全国1位。1年制の最短コースで社会福祉士国家資格を取得できます。

社会福祉士養成科
合格者数全国1位。土日休みの「週休2日制」のコースと18:10授業開始の2つのコースから選べます。

社会福祉士養成通信科 一般
修了率約95%。きめ細かなサポート体制が、高い修了率につながっています。

踏み出そう
日本福祉教育専門学校では、福祉・医療の専門家を目指す皆様を全力でサポートします。まずは資料請求やオープンキャンパスで、学校の雰囲気を感じてみてください。






