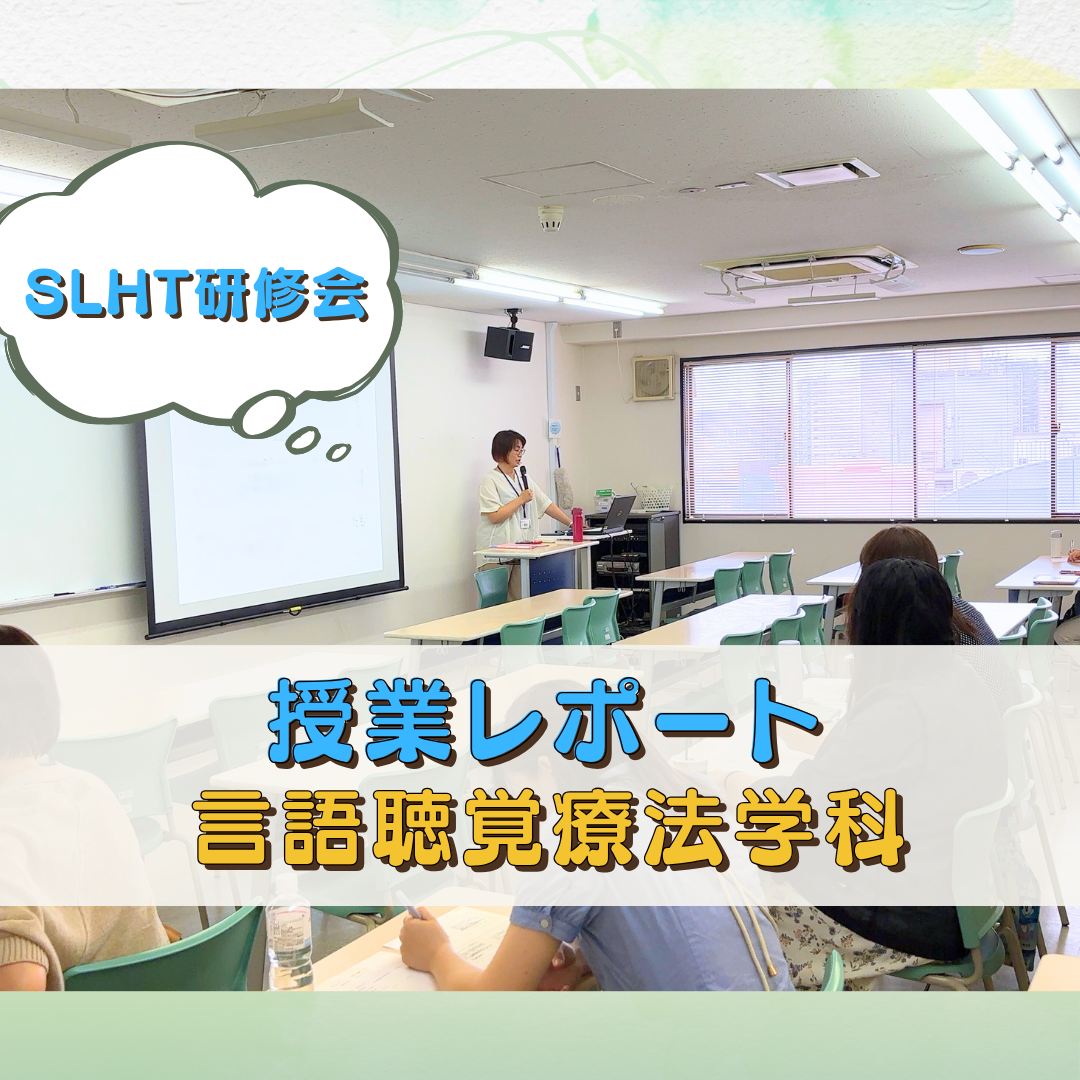- 通学部/学科一覧+-
2025/07/18
こんにちは!日本福祉教育専門学校です。
本日は、言語聴覚療法学科の授業風景をご紹介いたします。

161教室と162教室をZoomでつないだ合同授業。
黒川先生が2つの教室を行き来しながら進行する、臨場感のあるスタイルで行われました。
授業中には先生のユーモアあふれる話に笑い声があがる場面もあり、終始和やかで楽しげな雰囲気に包まれていました。
今回のテーマは「社会的処方」。
医療・福祉の分野で注目されている“社会的処方”や“社会参加の支援”に関する知識を深めながら、相手の社会参加を「見つける」視点を養うことが目的です。

授業の前半では、社会参加のかたちを広く捉えるために、「フォーマルなサービス(制度に基づいた支援)」と「インフォーマルなサービス(地域に根差した柔軟な支援)」についての整理が行われました。
たとえば、地域のスーパーにある「ゆっくりレジ」は、高齢者や障がいのある方にとって“焦らず買い物ができる安心な場”となりうる、インフォーマルなサービスです。
こうした「制度の外側」にある小さな配慮や取り組みにも、支援のヒントが詰まっています。

後半は実践的なワーク形式で進行。
まずは個別で資料を読み込み、「社会参加のバリエーション」や「その見つけ方」についてじっくり考えたあと、5~6人のグループで意見交換を行いました。
その後、グループでの話し合いをふまえて再び個別にワークを実施し、自分なりに学びを整理。
グループワークのあとに、黒川先生が教室を巡りながら学生一人ひとりに「どんなことに気づきましたか?」と問いかけていくスタイルで授業が進みました。
こうした丁寧な対話を通じて、学生たちの気づきがさらに深まり、学びが自分自身の言葉として定着していくのが印象的でした。
支援者として大切なのは、目の前の人が「社会とつながるための道」を共に探し、ときに示していけること。
そのためには、制度に頼るだけでなく、地域に眠っている資源に気づく力や、柔軟な発想が求められます。
たとえば、「誰でも使える場所」だと思っていた場所に、実は暗黙のルールがあって入りにくい人がいるかもしれない。
そうした気づきが、その人らしい生活の実現に直結する支援につながっていくのです。
この日の授業は、言語聴覚士を目指す学生たちにとって、“社会と人をつなぐ”という支援の本質に触れる貴重な時間となりました。
*+。+*+。+*+。+*+。+*+。+*+。+*
通学2年で国家試験受験を目指します。
言語聴覚士取得にご興味あるかたはオープンキャンパスへご参加ください。
ご来校お待ちしております(^▽^)/
◆言語聴覚士のオープンキャンパス◆
資格・仕事の内容、カリキュラム・国家試験・就職・入試・学費サポートなど目指す資格、入学に関する内容を教員・職員よりご案内します。
学生が校内の案内をしていますので、実際の様子も聞いていただく事が可能です!
■7月19日(土)・27日(日)13:30~15:15
*+。+*+。+*+。+*+。+*+。+*+。+*

合格者数全国1位。
専門実践教育訓練給付金対象。